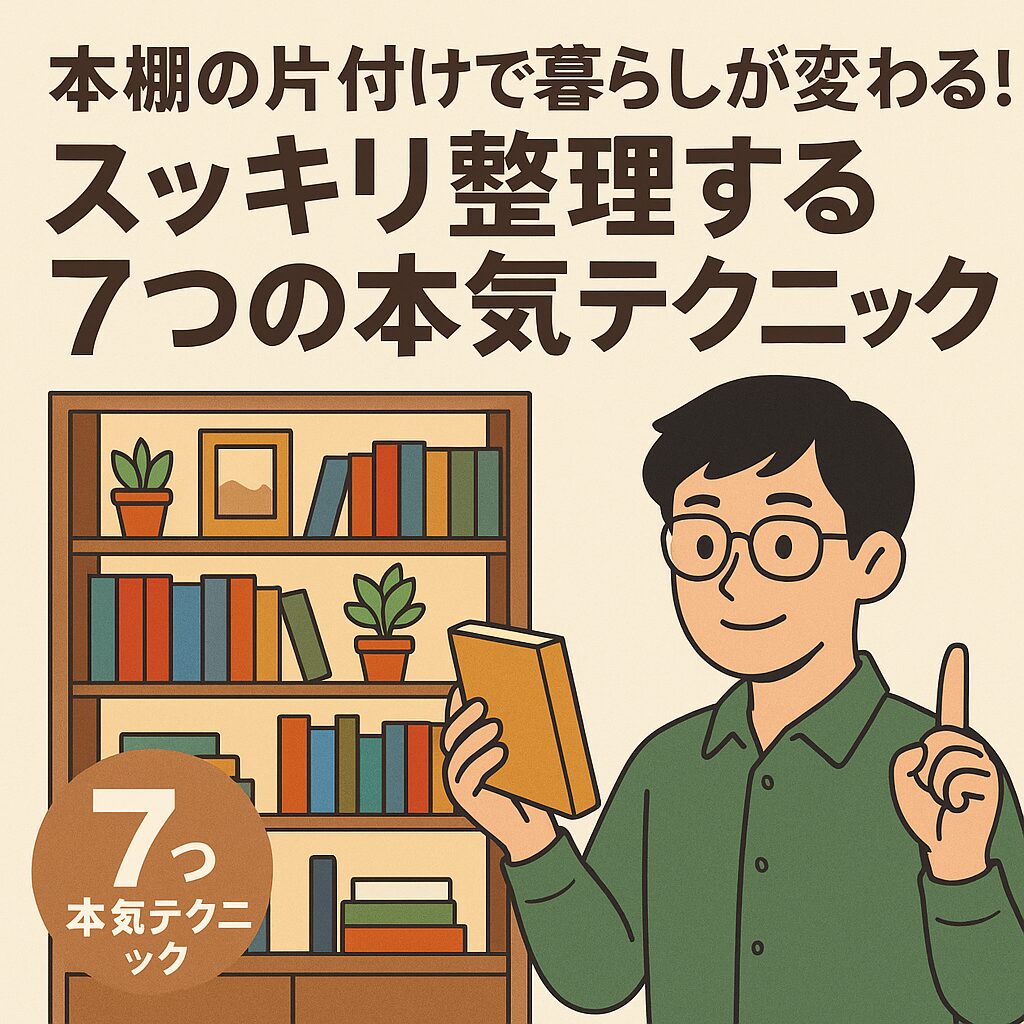本棚がパンパンで、もう入らない…」
「買った本がどこにあるか分からない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
本が好きな人ほど、気づけば本棚があふれていた…なんてことはよくありますよね。
買ったけど読んでいない「積読本」、思い入れのあるシリーズ、参考書、趣味の雑誌――どれも大切だからこそ、簡単には手放せない。でも、部屋の中で本が占めるスペースが多くなりすぎると、生活にちょっとした不便が出てくるのも事実です。
ちょっとした工夫を加えるだけで、本棚はもっと使いやすく、見た目もスッキリと変えられます。
そんな本棚をスッキリ整えるには、「ただ捨てる」のではなく、整理と収納の“コツ”を押さえることが大切です。
本の量や種類に合わせた工夫を取り入れることで、読書の楽しみを保ちながら、快適な空間が実現できます。
スッキリ整理する“7つの本気テクニック”はこちら
-
本棚に“役割”を与えて用途別に分ける
→ 読書用・保存用・資料用などで本棚を分ける整理法 -
ジャンルや状態ごとに分類して管理する
→ 小説、ビジネス、漫画、参考書、読了・積読・貸出などで整理 -
「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける
→ よく読む本・表紙が綺麗な本は見せて、古い本は隠す -
収納スペースを最大化するレイアウト術
→ 棚板の調整、縦空間の活用、隙間家具の導入など -
美しく見せるための配置ルールを取り入れる
→ 色・高さ・奥行きを揃えて整えるデザイン整理術 -
“余白”をあえて作って見栄え&出し入れUP
→ 詰め込まない本棚の方が逆に使いやすい&美しい -
読まない本の整理基準を持つ(処分・保留・譲渡)
→ 手放す基準を明確にし、片付けを加速させる考え方
本棚が片付かない原因はどこにある?
本棚の片付けは、単にモノを減らすことではなく、「本と心地よく付き合うための環境を整えること」です。大切なのは、自分の読書スタイルに合った分類や収納、そして“見せる楽しみ”や“使いやすさ”を意識したレイアウトの工夫です。
本があふれるのは悪くないけど…
本がたくさんあること自体は、決して悪いことではありません。それだけ知識や感性を大切にしてきた証ですし、本がある空間には温かみがあります。ただし、問題になるのは「量」ではなく、「整理の仕方」です。つまり、増え続ける本に対して、きちんと収納や管理ができていない状態が“片付かない”原因となるのです。
大切なのは、“本を減らす”ことではなく、“本の居場所を決めてあげる”こと。今どれだけの本を持っていて、どれを読んで、どれが積読状態かを把握するだけで、片付けの意識が大きく変わります。
「本が多い=悪」ではなく、「本が迷子=困る」が本質的な問題なのです。
「とりあえず突っ込む」が片付かない元凶
片付かない本棚でよく見かけるのが、「空いたところにとりあえず突っ込む」という収納スタイル。これは一時的には楽ですが、長期的には管理ができず、どこに何があるのか分からなくなります。そして、また同じ本を買ってしまったり、必要な本が見つからなかったりという悪循環に陥ります。
こうした“突っ込み式収納”を防ぐためには、「分類のルール」を決めることが重要です。たとえば、「シリーズ物は必ず左端から」「ジャンルで棚を分ける」「積読は下段にまとめる」など、自分に合った法則を持つことで、自然と整った本棚になります。
本棚の収納量と持ち本量のバランス
「もう入らないから床に積むしかない…」という状況になっていませんか?これは、収納量と持っている本の量が合っていないことが原因です。本棚に入らないほどの本を所有している場合、新たに本棚を追加するか、本を見直して整理する必要があります。
まずは本棚の容量を把握し、「今の収納に無理なく収まる冊数」に絞るのがポイント。意外と読み返さない本、ダブって持っている本があるかもしれません。一度「本の棚卸し」をして、持ち本と収納のバランスを調整しましょう。
読んでない本・読む予定の本の整理法
“積読”は読書家あるあるですが、数が増えすぎると本棚を圧迫してしまいます。「いつか読む」は大事にしたい気持ちですが、整理の観点からは「いつか」ではなく「どれだけ?」を考えることが大切です。
おすすめは、「積読ゾーン」を本棚に作ること。そして、そのエリアがいっぱいになったら、新たに本を買うのは一度ストップ。読んだ本を「読了ゾーン」に移すことで、進捗が目に見えて分かるようになります。この流れができると、無理なく本の整理が習慣になります。
本棚に“役割”を与えるという考え方
本棚をただの収納家具と考えるのではなく、「テーマ別に役割を与える」と、格段に使いやすくなります。
たとえば、1つの棚は仕事用、もう1つは趣味用、別の棚は子どもと共有用…と分けることで、どこに何があるかが一目で分かるようになります。
また、使用頻度や本の重要度に応じて、「よく使う本は手前」「資料本は奥」といった配置にすると、探し物の時間がグンと減ります。本棚に“役割”を与えることで、自分だけの整理ルールが確立され、片付けが自然とラクになるのです。
本棚整理!捨てなくてもできる分類テクニック
読書好きにとって「捨てる」はつらい選択肢。でも、片付けのゴールは本を手放すことではなく、“必要な本を必要なときに取り出せる”環境をつくることです。分類や整理の工夫次第で、本を減らさなくてもスッキリとした本棚は実現できます。
ここでは、捨てずに片付けを進めるための整理・分類のテクニックを具体的に紹介します。
ジャンル分けで本棚がスッキリ
最も基本的かつ効果的なのが「ジャンル分け」です。
小説・ビジネス書・参考書・雑誌・漫画・写真集など、カテゴリごとに棚を分けるだけで、本棚全体がとても見やすくなります。たとえば、「上段は漫画、中段は実用書、下段は雑誌や資料」といったレイアウトにするだけでも探しやすさが大幅にアップします。
さらにジャンルごとにラベルを貼ると、自分だけでなく家族とも共有しやすくなります。ジャンルごとにエリアを分けることで、増えてきたときに「どこを整理すべきか」も判断しやすくなります。本が多くても、整理されていれば“片付いて見える”のが不思議です。
「読了」「積読」「貸出中」で分ける方法
分類方法はジャンルだけではありません。読書の“状態”で分類する方法もおすすめです。
たとえば、「読了=もう読んだ本」「積読=まだ読んでいない本」「貸出中=他人に貸している本」といった区分けを本棚の一角で行うと、読みたい本の管理がとても楽になります。
読了した本は「再読するか」「手放すか」を検討するタイミングにもなり、積読は自分への読みたい本リストとして機能します。また、貸出中の本は、メモや付箋で「誰に貸したか」を記録しておくと便利です。本を読む楽しみを“見える化”することで、読書のモチベーションにもつながります。
背表紙の色で整理するカラーファイリング
視覚的に美しい本棚を作りたい人におすすめなのが、「背表紙の色で分類する」カラーファイリングです。これは特に文庫本や漫画本など、似たサイズ感の本が多い場合に効果的で、まるで雑貨屋さんのようなおしゃれな本棚に仕上がります。
同系色をまとめることで統一感が出て、インテリアとしての満足度も高まります。ただし、実用性はやや下がるので、「見た目重視」の棚と「実用重視」の棚を分けて配置するのがコツです。好きな色を中心にテーマカラーを決めて並べてみると、自分らしさのある本棚になりますよ。
シリーズもの・続き物の並べ方ルール
漫画や小説などのシリーズ物を持っている方は、「巻数順に並べる」だけでなく、いかに美しく・機能的に並べるかも考えてみましょう。シリーズは一か所にまとめ、途中までしかないシリーズは“あと何冊必要か”をメモするスペースを設けるのもおすすめです。
また、最新巻だけが他の場所にあると探す手間がかかるため、「シリーズ専用棚」を作ってしまうのも手。お気に入りの作品は特別な位置に配置することで、見るたびにワクワクした気持ちになります。読書の流れをスムーズにするためにも、シリーズは一箇所にまとめるのがベストです。
本の“見せる収納”と“隠す収納”の使い分け
すべての本を見えるように並べる必要はありません。表紙が美しい本やインテリアとして飾りたい本は「見せる収納」、古くなって読む機会が少ない本や参考資料などは「隠す収納」として分けておくと、部屋全体が整って見えます。
見せる収納には、表紙を前にして立てかけるディスプレイラックや、オープン棚が向いています。一方、隠す収納には、扉付きの本棚や、引き出しボックス、収納ケースなどを活用するのが◎。この“使い分け”ができるようになると、整理の自由度もぐっと広がり、気分や季節に合わせたレイアウト変更も楽しめるようになります。
本棚のスペースが足りない!収納力アップの工夫
本好きにとって避けて通れないのが「スペース問題」です。
本棚に本をきれいに並べたいけれど、収納力が足りない…。そんなときは、本棚の使い方を見直すだけで収納量がぐんと増えることがあります。
ここでは、今ある本棚をもっと賢く使うための収納力アップ術を紹介します。
棚板の高さを調整するだけで収納力UP
本棚の多くは、棚板の高さが可動式になっているものが多いですが、意外と活用されていないことも多いです。高さが合っていないせいで、ムダな空間ができていませんか?
例えば文庫本しか入っていない段に30cmの空間が空いていたら、その分がまるまる「死にスペース」になっているんです。
収納力を最大化するためには、まず本のサイズに合わせて棚板の高さを微調整してみましょう。無駄な空間をなくすだけで、同じ棚でも1.2倍〜1.5倍ほど多く本を入れられることがあります。とくに文庫やコミックスが多い人は、上下をギリギリにするだけでかなりスペースが増えますよ。
横に詰めない!“余白”がポイント
「たくさん入れたい」と思って本をぎゅうぎゅうに詰めていませんか?
実はこれ、逆効果。本棚が窮屈に見えるだけでなく、読みたい本が取り出しにくくなる原因にもなります。収納力を上げるためには、「一列に詰め込む」ではなく、「余白を活かす」考え方が大切です。
余白を作ることで視覚的にもゆとりが生まれ、本の取り出しや戻す作業がストレスなく行えます。実際に使いやすい本棚は、8〜9割程度の収納率をキープしているものが多いです。ぎゅうぎゅうに詰まった本棚よりも、少しだけ余裕のある棚の方が美しく、管理もしやすくなるのです。
二列収納・ダブル収納は本当に便利?
奥行きのある本棚では「前後に本を並べる二列収納」や「ダブル収納」がよく使われますが、これは一長一短です。確かに収納量は増えますが、奥の本が見えなくなるため、読まなくなる可能性が高くなります。実際、「存在を忘れていた」「同じ本を二度買った」などのトラブルも…。
どうしても二列収納をする場合は、奥にあまり読まない本や保存用の資料などを入れ、手前には日常的に読む本を並べるのがベター。ブックスタンドや仕切りボードを使って「ここから前列」「ここから後列」と分かりやすくすると、混乱を防げます。
本棚の上・下・横も有効活用する方法
本棚の「上部」や「側面」「下の床スペース」も立派な収納エリアです。たとえば、本棚の上に収納ボックスを置いて雑誌やアルバムを入れたり、壁にブックホルダーをつけて“浮かせる収納”をしたりすることで、収納範囲が広がります。
また、本棚の下にスライド式の収納ケースを入れれば、文庫本や薄い本をきれいに保管できます。サイドスペースにはS字フックやウォールポケットを使って、小物類や付録、ノートなどを収納するのも便利。目線を変えると、「まだ使える場所」が意外とたくさん見えてくるはずです。
スリム本棚&隙間収納アイテムの活用術
「部屋にスペースがないから本棚を増やせない…」という人には、スリムな本棚や隙間収納アイテムがおすすめです。家具の隙間やベッド横、デスクの横など、数センチのスペースでも本棚に変えることができます。
たとえば、幅15cm〜20cmのスリム書棚は、漫画や文庫本の収納に最適。キャスター付きなら移動も簡単で、お掃除もラクです。100均やホームセンターでも、隙間用収納グッズが多数販売されており、工夫次第で大容量の収納を確保できます。
狭い部屋でも、諦める必要はありません。収納の“縦使い”や“奥行きの工夫”で、スペースを最大限に活かす方法はたくさんあるのです。